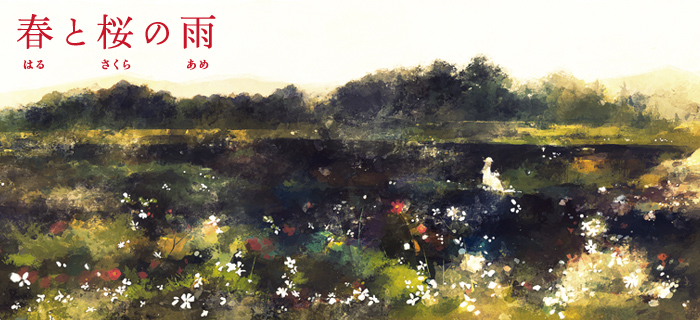ゴールデンウィークは帰ってきなさい、と田舎の母から電話が入った。私は耳と肩の間に携帯電話を挟んだまま、ビールのプルタブを起こした。
「なんで?」
「ちょっとね、ドイツ語を教えて欲しいのよ。あんた大学で勉強してたでしょう?」
「もうほとんど忘れちゃったよ。誰に教えるの? せっちゃん? 高校の第二外国語でやってるの?」
「まあそれはこっちにきてから言うわ」
「めんどくさーい」
「ふきのとう、いっぱい採れたから帰りに持ってっていいわよ」
「二十九日に帰ります」
通話を切ると、背後のテーブルで菜の花とタラの鍋を煮ていたコハルちゃんが情けない声を上げた。
「せんぱぁい、月末の合コン行くって言ってたじゃないですか」
「あ、忘れてた」
「せっかく弁護士さんたちなのに」
「お風呂に入りながらイエローサブマリンごきげんで歌ってくれる人いるかな」
「先輩の趣味ありえない。その基準で行くと私の父さんオーケーになっちゃいますよ」
可愛げのないことを言う後輩だが、火加減を小まめに見てくれたり、良い具合に煮えた豆腐をよそってくれたりとなかなか優しいところもあるのだ。私は緑の冴えた菜の花をポン酢につけながらコハルちゃんの頭をなでた。
「まあ、お土産買ってきてあげるよ」
私の田舎はたいそう北の方にある。米どころで、お酒がおいしい。
連休の初日、金色のビル灯が輝く深夜の東京駅から夜行バスに乗り込んだ。一昨年の正月以来、久しぶりの帰郷だ。隣席は、疲れた顔をしたリクルートスーツの若い女の子だった。就活の帰りだろうか。くまの浮いた横顔を見ているうちに、こんぺいとうを舌へ乗せたようなうす甘い気持ちになった。
かつて、私はこの子とまったく同じように疲れた身体を丸めて夜行バスに揺られていた。大学四年の春、卒論の合間を縫ってたびたび就活のために上京し、ヒールの踵がすり切れるまで山手線の内側を歩き回った。卒業ぎりぎりで内定をもらい、同じく東京の会社に勤めることになった恋人と手に手をとって上京して、それから八年。二回転職し、恋人とは彼の転勤をきっかけに別れた。いつのまにか言葉づかいも標準語になり、こちらから言い出さない限りは北国の出身だと誰にも気づかれないようになった。人の多さにも慣れたし、夜が明るいのにも慣れた。
ただ一つ慣れないのは、東京で買える野菜の味気なさだ。他県から取り寄せている品が多く、輸送の間に鮮度が落ちてしまうのか、スーパーに並んでいるものはことごとく水っぽくて香りが薄い。そして、高い。実家では、祖父母の畑に生えた野菜を採ってすぐに食卓へ並べていた。土の香りがなければ舌が満足できない。ふきのとう、と胸で呟いて、橙色の照明が点滅する長いトンネルで目を閉じた。
翌朝、私は青々と光る白神山地を見上げてバスを降りた。空気が凛と澄んでいる。東京ではもう二週間も前に散ったのに、駅前の植え込みではまだ桜の木が白い花を残していた。
実家へ辿りつくと、ちょうど母と兄嫁が朝食をとっているところだった。父と兄はもう勤めに出かけ、祖母はまだ奥の部屋で眠っているらしい。夜行バスであまり眠れなかった旨を伝えると、兄嫁の真沙子さんが箸を置いて二階に布団を敷いてくれた。
典型的な田舎のヤンキーだった兄がどうやってこんなにいい娘さんをつかまえたんだろう。母の電話によると、真沙子さんは毎晩祖母をお風呂に入れる介助までやってくれているらしい。長旅をねぎらってくれる兄嫁に枕をたたかれ、私は子供のような気分で布団にもぐり込んだ。
スリッパの足音が遠ざかるのを待って、うす暗い天井を見上げる。子供の頃にはお化けの目玉に見えて仕方がなかった、木目の天井。私の実家は広い。二階には、私が寝ている座敷のほか、使っていない部屋がまだ三つ四つある。腕の良い料理人だった祖父の代には民宿をやっていた。後を継ごうとしていた父が膝を痛めて厨房に立てなくなり、結局祖父が喜寿の年に民宿は看板を下ろした。その翌年、祖父は亡くなった。
昼ごはんは、てんぷらだった。さりげなくふきのとうばかり食べていたら、母に「いい加減大人になりなさい」と呆れられた。食事を終えると、母はお盆に祖母の分の食事を乗せて奥の部屋へ入っていく。私は真沙子さんの皿洗いを手伝った。濡れた皿をふきんで拭きながら泣きぼくろが色っぽい兄嫁の横顔へ声をかける。
「ばあちゃん、調子どうですか」
「実はね、半年ぐらい前から徘徊がはじまっちゃって」
「はいかい?」
「なんかね、明さんを幼稚園に迎えに行かなきゃって思うみたいなのよ」
明とは定年間際の私の父のことだ。今年で五十九になる。
「時計が止まってるね」
「止まってるっていうより、だんだんさかのぼるみたい。少し前までは仕事に行かなきゃって言ってたから。明さんが成人した後、縫製工場に勤めてたでしょ?」
「そうかあ」
「夜中に目が覚めたときだけ、自分がいつの年代にいるのか分からなくなるみたい。でも、それ以外はしっかりしたものよ? 私のふきのとう味噌の作り方が下手だって、お手本を見せてくれるんだから。あと、ここ数年は公民館の集まりで、草木染めにも凝ってるの。かわいいでしょ、この鍋つかみ。おばあちゃんが作ったのよ」
真沙子さんはそばに置かれたタンポポ色の鍋つかみを指さした。確かに良い品だった。大きくて使いやすそうで、そのうえ色合いが優しい。皿洗いを終えた真沙子さんは濡れた手をふきながら壁時計を見上げた。
「手伝ってくれてありがとね。二時から居間で授業がはじまるらしいから、頑張って」
「真沙子さんも知ってるんですか。生徒、誰だかわかります?」
「それははじまるまでのお楽しみ。でも、すっごく真剣よ。本気でドイツ語を勉強したいんだって」
時間になって、いちおう用意してきたドイツ語の初級テキストを手に居間へ向かう。
ふすまを開けると、そこには御年八十二歳になる私の祖母がきちんと正座して座卓の向こうに座っていた。これからどこかに出かけるのか、清潔感のある紬の着物を着ている。私はあっけにとられて口を開いた。
「ばあちゃん、私ここでこれから授業するんだよ。せっちゃんか誰か分からないけど、ドイツ語教えるの。もしかして、これから友達でも来るの?」
「おれだ」
「は?」
「ドイツ語を教えて欲しいのはおれだ」
よく見れば、祖母の手元には丁寧に削られた黒鉛筆が三本と赤鉛筆が一本、下敷きの差し込まれたノートと新品のドイツ語辞書が揃えられていた。
ぽかんと突っ立ってないで座れ、と促され、私は祖母と対面する座布団へ縮こまりながら膝を落とした。
沈黙が下りる。
祖母は真剣だ。
「ええと、……ドイツ語? なんでまた」
「理由を聞かんと教えんのか?」
「いえ、そんなわけでは」
「じゃあいいだろう。早く始めてくれ」
ノートを開いて貰って、さらに驚いた。真新しいノートの初めの三ページには、びっしりと几帳面な字で大文字小文字のアルファベットが十個ずつ練習で綴られていた。ご丁寧に発音記号まで書き込まれている。
これは大変なことになった。祖母は本気で、私が帰郷しているたった四日間でドイツ語を学ぶつもりなのだ。
私は祖母の書いたアルファベットを指さしながら、まずは基本の発音練習から始めた。アー、ベー、ツェー、デー、エー、エフ、デー。祖母はゆっくりと口を動かし、一音一音噛みしめるように発声していく。ハー、イー、ヨット、カー、エル、エム、エン。乾燥して白い筋の入ったぶ厚い爪がゆっくりと自分の書いた文字を追う。オー、ベー、クー、エル、エス、テー、ウー。舌を歯の裏で動かさなければいけない音が苦手なようだ。それはそうだろう、日本語はあまり口の中で舌が動かないのだ。ファオ、ヴェー、イクス、イプシオン、ツェット。ぜんぶ読み上げたら、またはじめから。
二時間かけてアルファベットの発声と「はじめまして、私の名前はホソバタチヅコです」といった短い挨拶の構文をいくつか練習した。祖母は丁寧にノートを取り、私に言われるまま単語のアクセントの位置に黒丸を打った。詰め込んでもはかどらないので、今日はここまでにしよう、とうながすと祖母は頷いた。正座した膝にしわの寄った手を乗せる。
ありがとうございました、と生徒が先生へするような丁寧なお辞儀をされ、私はまた馬鹿みたいに口を開いて呆気にとられた。慌ててこちらも正座を直し、お疲れさまです、となんだかちぐはぐな言葉を返す。
夕飯のあと、風呂から上がると真沙子さんが楽しげな足取りで近づいてきた。
「さっき、おばあちゃんの部屋の前通りかかったらアーとかヴェーとか声が聞こえたわ」
「なんであんなにやる気なんですか?」
「恋よ、恋。草木染めの教室でお世話になってるドイツ人の先生が、すごくかっこいいおじいさんなのよ」
「ばあちゃんすごいなあ、もう八十過ぎてるのに」
台所へ向かう途中で、会社から帰ってきた兄と鉢合わせた。よ、とお互いに片手を持ち上げてすれ違う。五つも年が離れているので、あまり話すことはない。ビールを一本貰って居間を覗くと、湯上がりの父が背中を丸めて足の爪を切っていた。普段一人で暮らしていると、なんだか同じ家の中にたくさんの人間がいる感覚に慣れない。
二階に上がって酒を飲み、とろとろとまどろんでいると、夢うつつに声を聞いた。母の声と、もう一つ。祖母の声だ。なにかやりとりをしている。気になって、私は布団から起き上がった。階段へ近いふすまのそばで耳を澄ませる。祖母は、どこかへ行きたいようだった。もどかしげにむずがっている。
じゃあ一緒に行きましょう、風邪引かないようにコートも着て、と母は柔らかく促した。そして、玄関の戸が開いて閉まる音がした。
翌朝、早めに目が覚めて台所へ向かうと、真沙子さんがウインナーを炒めるいい匂いをさせながら父と兄二人分の弁当と全員の朝食を作っていた。
「お母さんは?」
「まだ寝てるわ。昨日の夜、おばあちゃんに付き添って隣町まで行ったらしいから」
「もしかしてあれ、毎晩やってるの?」
「毎晩ってわけじゃないけど、そうね、二日に一度くらい」
「しんどそう」
「夜桜きれいだったって言ってたよ」
母らしい言葉だ。
朝食のあと、真沙子さんは祖母を車に乗せて近くの公民館へ向かった。草木染めの教室があるらしい。母もクリーニング屋のパートに行ってしまったので、私は手持ちぶさたに庭に繋がれた柴犬のゴローをつれて散歩に出かけた。もう十三歳をこえた老犬だ。あまり早く歩けないのでゆっくり進む。
散りかけの桜の白い花弁がころころとアスファルトを転がっていく。久しぶりに市内を回ると、市役所の建物が新しくなり、駅前にショッピングモールが出来ていた。石畳の坂を上って、桜がざかざか咲いている中央公園へ向かう。
砂場で、ちいさな息子を連れた幸田君を見つけた。高校時代の同級生だ。仕事が休みなのだろう、大きな背中を丸めて息子と一緒に砂山を作っている。そばへ寄って肩を叩いた。
「幸田君だ」
「あれ、細畠」
「おげんきですか」
「げんきげんき」
「息子くんいくつになった?」
「よっつ。我が家のげんきな小猿ちゃんよ」
黒目がちな小猿ちゃんはゴローに気づくとぽてっとしたお尻を持ち上げ、きゃあ、とも、みゃあ、ともつかない歓声とともに脂の抜けた毛並みへ抱きついた。慣れているのだろう、ゴローは目を細めて尾を揺らす。
「細畠は? 東京どうよ」
「不況だし、楽しくないし、好きな男も出来ないし、たまに嵐の海でどうしようって立ち往生してる気分になるよ」
「うはは」
「でもまあ、なんとかかな」
「うまいもん食ってる?」
「食ってる食ってる」
「じゃあ大丈夫さ」
笑う幸田君の頬骨の下に、小さな青痣を見つけた。
「美香子げんき?」
「このまえ入院した」
言いながら、幸田君は骨ばった手のひらを息子くんの頭へ乗せた。
「発作でさ、こいつを叩きかけちまったみたいで、パニックになって自分の手のひらを包丁で切った」
美香子は、高校のクラスのマドンナだった。容姿に恵まれた子で、息子くんにも受け継がれた大きな瞳と桜色の唇が濡れた花のように愛らしく、芸能界に携わっていた時期もあったらしい。幸田君と結婚し、子供を産んだ二十代の半ばから心身のバランスを崩して入退院を繰り返すようになった。人付き合いが得意な方ではなかった。育った家庭が不仲で、不安定だった。幼い頃から、彼女の容姿に対する周囲の反応があまりに過剰だった。さまざまな理由があるだろう。いつのまにか美香子は、容姿でばかり人に愛される自分は、年をとって今の姿を失ったら、誰にも見向きされなくなるのではないかという悲しい強迫観念を胸へ巣くわせるようになった。普段はけして表に出さない。けれど、雨が降ると、美香子は幸田君を叩く。なにかを確かめるように、なんどもなんども叩く。
私はふと、休み時間に机を合わせて一緒にプリントを解いていた美香子の手を思い出した。握り込むような、妙なシャーペンの持ち方をしていた。よくノートの端にハリネズミの落書きをしていた。あの無防備な手が愛する男を打ち、子供へ振り上げられ、冷たい刃物を握って肉の薄い手のひらを切り裂いたのか。
「つらいね」
「大丈夫さ。春先はいつも荒れる。夏になれば落ちつくんだ。それに、一番戦ってんのは美香子だからなあ」
なんでもないことのように言って、幸田君はジーパンの尻についた砂を払った。立ち上がり、息子くんの小さな手を握る。弁当買ってママんとこ帰るか、と幸田君が呟くと、息子くんはまた嬉しそうに歓声を上げた。
「まあ、次の同窓会のときまでには持ち直させるからさ、細畠もそっちでふんばれよ。また飲もうぜ」
「おう」
十代の頃、私は幸田君のことが好きで好きでたまらなかった。息子くんをあやしながら桜並木の奥へ歩いて行く幸田君は、あいかわらず格好良かった。けれどもう彼は、誰もがはじめに歩いている舗装された太い道を外れ、大切なものを手に包んで進む彼だけの荒野へ足を踏み出していた。けして触れることの出来ない、遠く清らかな背中だった。
ゴローの背中についた桜の花びらを払って、私は家へ戻った。
日を追うごとに、祖母はみるみる上達をみせた。びっくりするほど入念に授業を復習している。特に、発音や会話文に気を配っているようだ。一度授業でなぞった文章はけしておろそかにしない。三日目には、こんにちは、こんばんは、ごきげんいかが? どこへ行くの? 今夜は良い晩ですね、などの基本会話を口に出せるようになった。
授業の終わりに、祖母はめずらしく私を引き止めた。
「舞」
「はいはい」
「これは、この言い方であってるのか?」
辞書を引きつつ祖母が私に聞いたのは、ほんとうに他愛ない日常の会話文だった。文法も語順もきちんとあっていたので、それであってる、と頷いた。
「八十二歳ですよ?」
信じがたい授業の成果を報告すると、お茶の湯飲みを手に包んだ真沙子さんは楽しそうに頷いた。
「人ってほんとに一生かけて学ぶ生き物なのね」
「そんな慣用句の枠を越えてると思う。超人だよ」
「それこそ恋の力でしょう」
真沙子さんは本気なのか冗談なのかわからない調子で言い、私の湯飲みにほうじ茶を足してくれた。湯飲みの下には、木綿のコースターが敷かれている。これも祖母が草木染めの教室で作ったもので、桃の葉で染めたのだというオリーブ色が美しい。晩年の豊かな趣味として、祖母はとても楽しく教室に通っているようだ。腰を痛める前には庭いじりが好きだったこともあって、植物を扱う作業が性に合うのだろう。
他の家族が寝静まった夜中、私たちはいっしょにお茶を飲むようになった。真沙子さんが遅くまで起きて夕飯の後片付けをして、代わりに早めに床についた母が夜中に起きて祖母の夜歩きに付き合う。そんな風に家庭内の分担が出来ているらしい。
「どれだけ良い男なんですか、そのドイツ人の先生」
「明日、公民館一緒に行く?」
「行きます」
「ちょうど、最後の日なのよね」
「なにがですか?」
「ふふふ」
真沙子さんは笑って答えない。おやすみ、と手を振られた。
真夜中、初日と同じ話し声で目が覚めた。
なんだか母の声の歯切れが悪い。不思議に思って一階へ下りると、祖母にコートを着せかけた母は眉をひそめて足首を撫でていた。私を見て、驚いた顔をする。
「あら、起こしちゃった?」
「どうしたの」
「おばあちゃんが散歩に行きたいって言うんだけど、母さん寝起きに足つっちゃって。ちょうどいいわ、あんた、ちょっと一緒に行ってきて」
「いいけど」
おばあちゃんちょっとまっててね、と祖母の肩に手を当て、歩み寄ってきた母は私の耳へ低くささやいた。
「ぜったいに目を離さないでね。できれば手か肘か、おばあちゃんの身体のどこかにずっと触れていて。あと、たまによく分からないことを言うかも知れないけど、否定しないでゆっくり話を聞いてちょうだい。二十分ぐらいしたら落ちついてくるから、帰ろう、ってうながして帰ってきて」
私は頷き、急いでパジャマの上にコートをはおった。
祖母は授業の時とは打って変わった無防備な表情をしていた。不思議そうに私の顔を見ている。触れていて、と言われても祖母と手を繋いだのはもう二十年以上前の話だ。どこに触れるべきか迷った挙げ句、私は腰の曲がった祖母の背へ手を添えた。軽く促して、玄関をくぐる。
夜風には花の香りが混ざっていた。一月には積雪が五十センチを越えるこの地域にも、遅い春がやってきている。
「ばあちゃん、どこに行きたい? 公園とか行く?」
あてもなく歩き出しながら問いかけると、祖母はまたガラス玉のように澄んだ眼を私へ向けた。孫の私を見る目つきではなかった。万華鏡を覗き込む幼児のような、もっともっと距離の遠い、未知のものをうかがう表情だった。祖母の焦げ茶の瞳が私の目をなぞり、鼻をなぞり、頬をなぞり、ようやく答えを見つけたように和やかに微笑む。
「ああ、ナナちゃんか。あんたも逃げるんだね。そうだよねえ、恐ろしいもんね」
ナナちゃん?
とっさに聞き返しかけ、言葉を飲み込んだ。否定しないでゆっくり話を聞いて、と母の声が耳に蘇る。私は曖昧な相づちを打ち、散歩の定番コースである中央公園の方へ祖母をいざなった。
しばらく言葉少なに歩き続け、園内の散歩道へ入る。見上げれば、空を埋めつくす夜桜が月明かりを溜めて光っていた。風が吹くたび、丸い花弁がざあざあと雪のように降り落ちてくる。花群に遮られて姿は見えないものの、近くの空港から飛び立ったのだろう飛行機のエンジン音がかすかに鼓膜をふるわせた。
皮膚の柔らかい祖母の指が、ふいに私の手を握った。
「ナナちゃん、あれは南の方に行くのかなあ」
「え」
「あたしはいつだって怖いんだ。あたしが死ぬことじゃないよ。あの人の頭に爆弾が落ちることが怖い。飛行機の音がするたび、何回だって祈る。どうかあの人の上に落とさないでください、あの人を無事に戻してください。どうしてもあの人の上に落とすなら、代わりにあたしの上に落としてください。何百回も、何千回も祈る。ちゃんとお祈りは、仏様に届いているんだろうか」
爆弾? 脈絡のない物騒な単語に私は混乱した。祖母は、いったいいつの時代へ遡っているのだろう。ひとまず調子を合わせようと、私はなるべく動揺を押し隠して口を開いた。
「あの人って、誰だったっけ」
「なんだいナナちゃん、熱でもあるのかい。達也さんに決まってるだろう。あんただって、冬に豊さんを一緒に見送ったじゃないか」
達也さん。
私の祖父の名だ。
それで、わかった。祖母の時間は、六十五年の時をこえている。祖母は花天井の向こうへ目を据えたまま、生々しく濡れた声で呟いた。
「あたしは馬鹿だからね、達也さんに言ったんだ。見たこともないもののために命を張るなんてそんな馬鹿げた話があるか、逃げちまおう。一緒に山へ入って、どこかへ行っちまおうって。そうしたら達也さんは言った。俺たちは、見たこともないもののために行くんじゃない。大切な人たちに、今年の、来年の、未来永劫の素晴らしい春の日を贈るために行くんだって。あの人はあたしなんかよりよっぽど美しい人なんだ。あたしはあの人に春を贈りたい。おぞましい鉄塊の雨じゃなく、この桜の雨を贈りたい」
桜が散り続けている。甘く香る風に痩せた身体をさらわれないよう、私は祖母の指を握りかえした。
おばあちゃんと呼んではいけない気がした。
「千鶴子さん」
乾いた口内を唾液で湿らせ、私は自分の頼りない荒野を見渡した。なにもない、ちゃんと物事を考えたこともない。それでも、震えながらひとつひとつの言葉を拾い集める。
「達也さんは、帰ってきます。片耳を無くして、それでもちゃんと無事に帰ってきます。そして、あなたと達也さんはその後、泥まみれで働いて、なにもない焼け野原から立派な家と畑を作り出してくれた。豊かで美しい町を築いてくれた。あなたの子供達は、幸せです。健やかな春の日を今日も味わっています。そして、今日から続く春の日は、その子供達が必ず守っていきます」
だから、うちに、帰りましょう。そっと手を引くと、千鶴子さんは私を見つめ、目を細めて頷いた。歩幅に気をつけながら、私は千鶴子さんの手を引いて桜の雨を抜けていく。ゆっくりと、静まりかえった町を歩いて家へ帰る。
玄関をくぐると、いつのまにか千鶴子さんは私のおばあちゃんに戻っていた。靴を脱ぐ途中にふと私を見上げ、驚いたように「なんだ、舞かい」と呟く。
「うん」
「あんまり夜更かしするんでないよ」
「はーい」
祖母が奥の自室に入るのを見届けて、私は二階の座敷へ戻った。体に、まだ夜風の花の匂いが残っているような気がした。
翌日、午前の授業で持参したテキストの第五課までが終わり、私は祖母のドイツ語講座に一区切りを付けた。アルファベット、発音の原則、動詞の現在形と人称変化、名詞の性と格など、基本的な項目はさらい終えた。あとは祖母の集中力なら、ラジオ講座でも充分ついていけるだろう。お疲れさまでした、と声をかけると、祖母は、ありがとうございました、と凛とした姿勢で頭を下げた。いつもはぞんざいに扱うのに、祖母はこの授業の間はずっと、私を「先生」として清潔に仰ぎ続けた。
昼食をとってから、真沙子さんのミニバンで祖母と一緒に公民館へ向かった。昨晩の夜風のせいか、道路沿いの桜はすでに半分以上の花が散り落ちていた。
年配の女性で賑わう草木染めの教室は、色紙を重ねた手製の花で飾り付けられていた。教室の先頭に置かれたホワイトボードもカラフルなペンで「アルベルヒ先生ありがとう!」と彩られている。ちづちゃん、とテーブルの一つを囲んだ同年代のおばあさん達に手招きされる祖母を見送り、私は講座の邪魔にならぬよう教室の一番後ろへ下がった。
隣に立つ真沙子さんの袖を引く。
「どういうことですか」
「つまり、今日がアルベルヒ先生の最後の出勤日なのよ。先生はずっとこういう教養講座をやりながら日本で造形アーティストとして活動してきたんだけど、もうお年だし、ドイツに帰るんだって」
真沙子さんが言い終わるのとほとんど同時に教室の前の扉が開かれ、大きな風呂敷包みを抱えた西洋人の男性が入室してきた。年頃は、六十代の半ばほどだろうか。鷲鼻にちょこんと銀縁のメガネを乗せた、背の高い人だ。教室を見回し、ハシバミ色の瞳が柔らかく笑う。みなさんごきげんよう、とよどみのない日本語で挨拶し、その男性は授業を始めた。今日は、前回けやきの葉で染めた毛糸を使って、冬の防寒具を作るのだという。春の温もりをぜひ冬まで、と歌うように口にして、アルベルヒ先生は丸まるとふくらんだ風呂敷包みをほどいた。
ぱっと教室の明るさが増した気がした。
まるで桜の花を積み上げたような、薄紅色の毛糸の山が教壇の上に現れた。教室のあちこちから拍手が上がる。みな、自分たちの卒業制作に満足しているようだ。アルベルヒ先生はにっこりと笑い、二十人ほどの生徒に三玉ずつ丸い毛糸玉を配っていった。生徒達はさっそく手元から編み棒を取り出し、それぞれの作品に取り組み始める。先生は一つ一つのテーブルをまわり、デザインや編み方についてのアドバイスをしていく。
熱心に手元に集中する多様な年代の女性達を見ながら、私はなにかを思い出しそうになった。この、暖かくて自由な空気は知っている。小学校の、図工の時間だ。粘土や画用紙を手元に広げ、「好きに作って良いよ」と優しく促されたときと同じ空気だ。
二時間の授業はまたたく間に過ぎ、何人かの生徒は手袋や子供の靴下など、ちいさな作品を完成させた。残りの毛玉は各自家に持ち帰って、自由に続きを作るらしい。「これからも、自分の中に世界のすべてを作ることが出来るみずみずしい赤ん坊が眠っていることを、忘れないでください。」そう言って、アルベルヒ先生は心地よい授業を締めくくった。拍手がわきたち、代表者らしい生徒の一人が歩み出て先生へ大きな花束を渡した。全員の記念撮影のあと、生徒たちは一人一人並んで戸口へ立った先生と握手をして帰っていく。私と真沙子さんは列に並んだ祖母のそばへ寄った。ありがとうございます、お元気で、など、にこやかな送別の順番が進み、祖母の番になった。祖母は先生と手を重ね、ゆっくりと口を開いた。
「ダンケ、シェーン。イヒ、ビン、フロウ、ジィツゥ、トレッフェン。ラッセン、ヅィ 、ウンス、ヴィダ、イルゲンダン、ズサメンコメン」
ほとんど日本語としか思えないたどたどしい発音だ。さすがに四日ばかりの授業では、難易度が高かったのだろう。語順もあやしい。けれど、けして恥じることのない潔い発声だった。アルベルヒ先生はみるみる目を丸め、花が咲くように微笑むと「Naturlich. 」と美しい発音で答えてくれた。祖母は大切そうに両手で先生の手を包み、やがて指を離した。
翌日、長い休暇が終わり、私が東京に戻る日がやってきた。
真沙子さんは祖母と作ったのだというふきのとう味噌を土産に持たせてくれた。お茶漬けにして、合コンで疲れて帰ってくるだろうコハルちゃんに食べさせてあげたいと思う。近くの商店街で地酒を買って戻ると、母が畑から摘んだばかりの野菜を袋に詰めて渡してくれた。父と兄にも別れを告げ、私は最後に祖母の部屋を訪ねた。
「じゃあね、おばあちゃん」
襖を開くと、祖母は卓の前でなにか作業をしていた。顔を上げ、私の別れの言葉に構わず、ちょっとこっちに来なさい、と手招く。
「なーに?」
「指を出しな」
大人しく人差し指を伸ばすと、指の根本がふわりとした暖かさに包まれた。
桜色の、毛糸の指輪だ。ふっくらとした開いた花のかたちをしている。呆気にとられて顔を向けると、祖母はすこし照れくさそうなしかめ面をした。
「どうせ手袋やマフラーを編んでやっても、若い者はかたちが古くさいとか言いそうだからね。デザインしたのは先生だ、それなら文句ないだろう?」
「すっごくかわいい」
ありがとうございました、と私はなるべく大きな声でお礼を言った。いつも、授業の終わりに祖母が言ってくれたように、すこしでも凛と響いてくれたらいい。
バス停まで車で送ってくれた真沙子さんが、別れ際に声をひそめて聞いた。
「それで、おばあちゃんの告白はどんな言葉だったの」
「ふふふふふ」
含み笑いでごまかして、私はバスへ乗りこんだ。
『ありがとう。あなたに会えて、とても楽しかった。いつか、いつか、きっとまたどこかでお会いしましょう。』
いつか、の示す先は、この世の場所ではないのだろう。
幼い頃に毎日見上げた青い山脈が視界から消え、私は人差し指の指輪へ目を落とした。私が、祖母と同じ誠実さで人に花を贈れるようになる日は、いつだろう。背もたれに身体を預けて目を閉じると、最果てに見知らぬ花が咲く、名もない荒野が広がった。
終